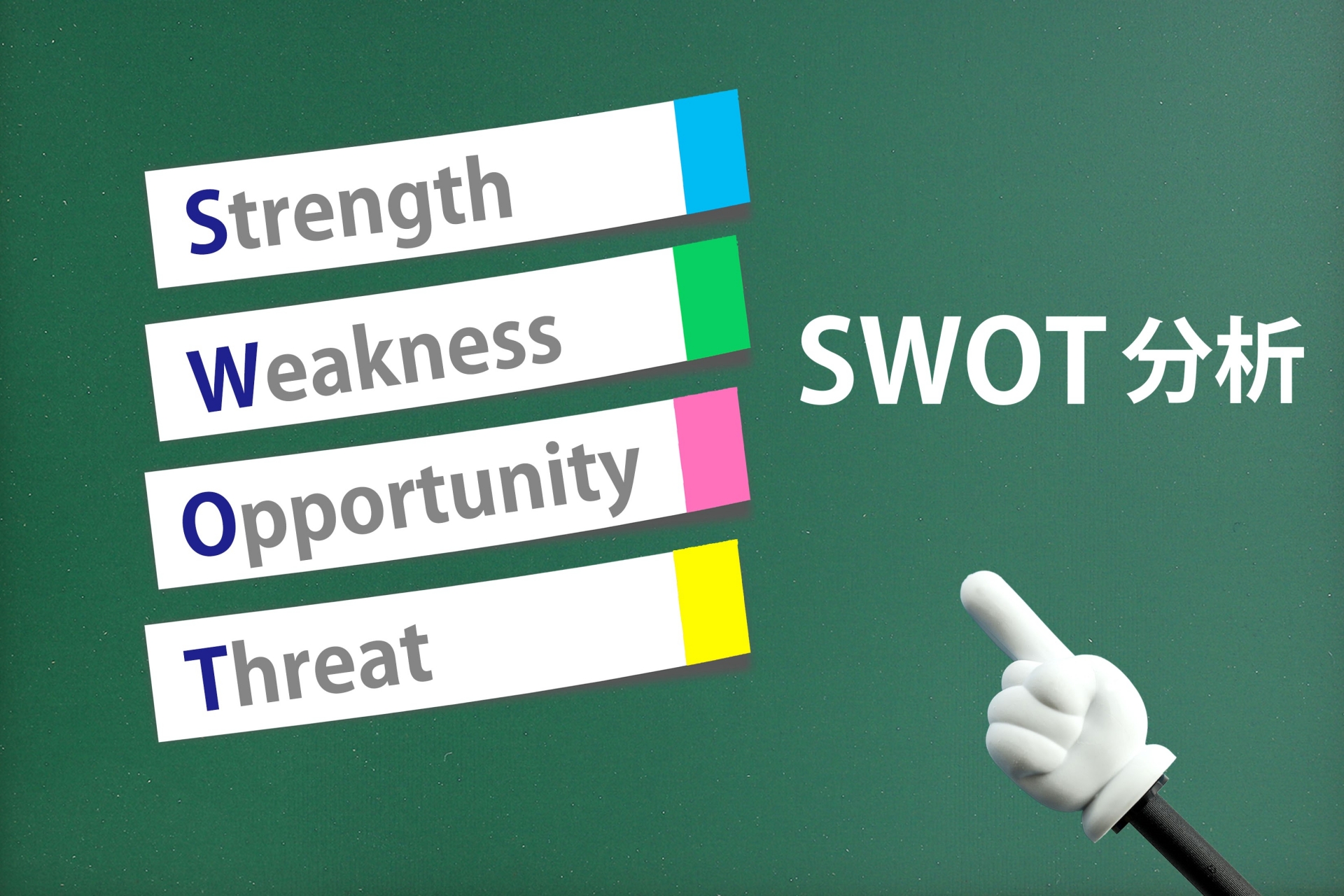新規事業を何故やるのかをはっきりとさせることが重要と以前書きました(→ご参照)。新規事業を何故やるのかを考えるには、既存事業の戦略方向性を再確認し、その方向性の中で新規事業をどう位置付けるべきかを検討する必要があります。この目的のために、私は以下のような手順でSWOT分析を使っています。SWOT分析は自社の「強み」や「弱み」、自社がおかれている環境の「機会」や「脅威」を分析し戦略を考えるツールです。SWOT分析自体はご存じの方も多いと思いますので、知っておられることを前提に書かせて頂きます。
SWOT分析は様々な用途で使いますが、企業がどこに向かうべきかという戦略方向性を抽出するためのSWOT分析は明確な手順があります。その手順は、「強み」×「機会」が最重要です。次に「脅威」でその方向性を補正します。「弱み」は、「強み」×「機会」で得られる方向性に触る場合のみ改善課題としてリストアップします。
ステップ1)「強み」×「機会」で大まかな方向性を出す
「強み」の抽出方法は、以前かなり詳細に書いたのでここでは割愛します。(→ご参照)「機会」を考えるには、既存事業の事業コンセプトを使います。だから、既存事業の事業コンセプト(どんなニーズや困りごとを持ったお客様に、そのお客さんにとって良いこと喜ぶことを、どんな自社の強みを活用して提供しているのか)が明確になっていることが前提です。そして、既存事業の事業コンセプトの「どんなニーズ、困りごとをもったお客様に」の部分が今とらえている「機会」ですので、これが当面継続するのであれば「機会」と認識します。修正が必要なら修正をしなければいけません。
修正のための切り口は、業界動向と競合動向です。業界動向とは、自社の顧客企業の業界の具体的な動向です。単純に言えば顧客企業の景気が良いのかどうか、当社に今後も注文をしてくれそうな要素があるのかということです。大手企業と違い中小企業の場合は、PEST分析などを使ったマクロ視点よりも、顧客企業の業界動向を中心に考えたほうが使える分析になる場合が多いです。競合動向とは同業他社の動向です。例えば、廃業が増えていることはどんな中小製造業でも「機会」になります。競合他社で業績が良いところがあればその原因を考えるのも重要です。「機会」の発見につながります。以上の手順で方向性が出てきます。
ステップ2) 脅威を回避する視点で方向性を補正する
「脅威」の切り口は市場と競合です。市場とは、自社の製品の市場や材料などの市場です。市場がシュリンクする、仕入れ価格が上がるなどはその典型です。競合の脅威とは競合他社や代替品の参入や競争の激化です。「脅威」がある場合は、基本はそれを克服するのではなく回避する方向に「強み」×「機会」で考えた方向性に補正をかけます。
ステップ3)「弱み」は必要に応じて改善策をリストアップ
「強み」×「機会」で抽出し、「脅威」で補正した方向性を推進するにあたり、障害となる「弱み」のみを課題としてリストアップします。方向性に障らない「弱み」は無視しても構いません。逆に改善が絶対に不可能なら「強み」×「機会」で抽出した方向性を修正しないといけません。
ステップ4) 新規事業の位置づけを考える
以上の手順を経て既存事業の戦略方向性の修正が完了するので、既存事業の事業コンセプト(どんなニーズや困りごとを持ったお客様に、そのお客さんにとって良いこと喜ぶことを、どんな自社の強みを活用して提供しているのか)も修正します。検討は通常は向こう3~5年ぐらいの中期計画なので、コロナ禍のような重大な非常時を除き通常は微修正になることが多いです。克服する弱みのリストアップも中期であれば具体的な内容が出せるはずです。
以上の作業で抽出した自社の戦略方向性の中に新規事業を位置づけます。大事なのは社内で新規事業を説明するときに、自社の戦略方向性を述べたうえで、矛盾なく新規事業の意義を説明できるかどうかということです。既存事業が今後狙っていく業界や業種、今後研ぎ澄ましていく自社の強みと新規事業で考えている内容に矛盾がないかが重要です。また、新規事業によって得られる新たなノウハウや技術が、既存事業にも役に立つ(相乗効果)が明確であればより説明がし易くなります。経営者自身が人、モノ、金を配分したいと本当に思うことができるかも重要です。中小企業は資金が限られているので、資金繰りや固定費が新規事業の足かせにならない範囲でできないといけません。また人的資源も限られているので、現場負担を増やさずスモールスタートで進めないといけないです。そのために外部リソースを積極的に使うことができるかも重要な視点です。
今回は新規事業が全社的な既存事業の中でどう位置づけられるかを考えるためのSWOT分析でした。